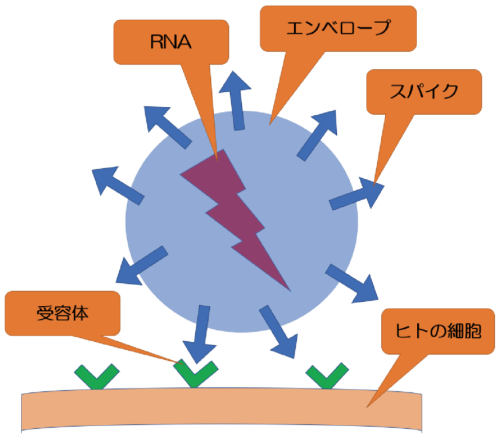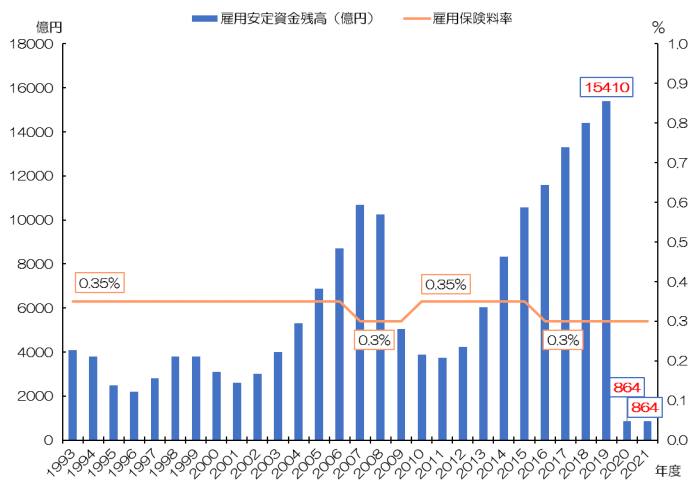2年目に致死率が上がったスペイン風邪
=100年前のパンデミックに学ぶ=
新型コロナウイルス感染症が中国・武漢市で確認されてから1年。しかし、その流行拡大は収まる気配を見せない。春先にささやかれた「夏になれば終息するのでは」との期待も虚しく、なお猛威を振るい続ける。そして2021年1月7日、菅政権は東京都と埼玉、千葉、神奈川3県を対象とする緊急事態宣言の発令を決定した。
実は、人類は100年前にも似た経験をしている。日本でも数十万人の死者を出した、スペイン風邪のパンデミック(世界的大流行)である。その歴史をひも解くと、「パンデミックの翌年」についても看過できない教訓が浮かび上がってくる。
コロナ禍に見舞われた2020年。10年以上前に書かれたある本が、新聞などの書評で相次ぎとり上げられた。歴史人口学者の故速水融・慶應義塾大学名誉教授が、1918~1920年に多数の死者を出したスペイン風邪についてまとめた「日本を襲ったスペイン・インフルエンザ」(藤原書店)だ。ちなみに速水は、新型コロナの流行が始まる直前の2019年12月4日に他界した。
初版は2006年。感染症専門家の間で、致死率が50%程度とされる「強毒性鳥インフルエンザ」に対する警戒感が高まった時期だ。中国などで家畜のトリからヒトへの感染が疑われる事例が発生し、「ヒトからヒトへの感染も時間の問題」とされていたのだ。
当時、私は新聞記者として厚生労働省の記者クラブに所属していた。このため、国が抗インフルエンザ薬のタミフルをどれだけ備蓄すべきかなどをめぐり、議論がにわかに盛り上がったのを覚えている。個人的にも、いざという時に備えて薬やマスクなどの備蓄を始めていた。
速水も重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行や強毒性鳥インフルエンザの発生を見て、スペイン風邪に興味を持ったようだ。ところが国内外の文献を調べるうち、「歴史教科書に全くとり上げられず、いくつも刊行される日本の歴史や近代日本の歴史といったシリーズものにも登場しない」ことに気づく。そのことが研究や執筆の動機となったという。
歴史の中で目立たない理由の1つは、第一次世界大戦の時期と重なったことだろう。他に関心を集める大ニュースが発生していたため、人々の印象に残りにくかった面がある。日本史上でも、大正デモクラシーや関東大震災などその前後にとり上げるべき出来事が多く、埋もれやすいのかもしれない。ただ日本に限れば、スペイン風邪の犠牲者の数は第一次大戦をはるかに上回る。
速水の著書に基づき、パンデミックの流れを簡単に振り返っておこう。記録に残る局地的流行は、スペインではなく米国カンザス州で始まった。1918年3月、欧州戦線に送るため駐屯地に集められた兵士の間で感染が広がったのだ。
そもそも「スペイン」という国名を冠しているものの、本当の震源地はよく分かっていない。スペイン風邪と呼ばれることになった経緯について、速水はスペインが中立国だったことが影響したと指摘している。交戦国と違って当時のスペインには情報統制がなく、インフルエンザについての報道が世界中に発信されたのだ。
その後、ウイルスは派兵などを通じて世界中に拡散する。大戦末期、感染の拡大で動ける兵士が減っていったエピソードも残っている。一方、この頃は国際航路が整備され、本格的なグローバル化が始まっていた。ウイルスが国境を越えて広がる環境がそろっていたのだ。
日本もその例外ではない。実際、1918年4月には巡業中の力士たちの集団感染などが報じられ始める。ただ、症状は比較的軽く、気温が上がる7月ごろまでには沈静化した。このころまでの流行を、速水は「春の先触れ」と呼んでいる。
本格的な流行を迎えるのは気温が下がる10月以降。全国で同時多発的に集団感染が発生した。火に油を注いだのが徴兵制度だ。初めて兵役に着く若者が召集されるのが12月1日と決まっていたからだ。大正期の日本で人々が団体行動をする代表的な空間は、学校と工場、そして軍隊だった。近代化が進んだ結果、制度的な「密」が生まれていたのだ。
ウイルスはそうした経路を通じ、一般の人に拡散。やがて鉄道運行や郵便配達などにも支障が出始める。被害が続出した関西では火葬場の処理能力を超えてしまい、棺桶が放置される事態も生じたという。当時の内務省の統計によると、この「前流行」では人口の約4割近くが感染し、死者は約25万7000人にのぼった。
しかしその後、翌年春までにいったん流行は下火になる。理由は定かではないが、気温が上がったことに加え、免疫を持つ人が増えたことも影響したはずだ。
しかし1919年の秋以降、再び「後流行」が日本を襲う。特徴的だったのは「前流行」に比べ死者が約12万7000人と半減する一方で、致死率が1.2%から5.3%へと上昇したことだ。速水はこの点について、別の型のウイルスが登場したわけではなく、同じウイルスが変異し、強毒化したためではないかとみる。新聞は「前流行」ほど騒がなかったものの、全国的な流行が断続的に生じ、終息したのは翌1920年春だった。
100年前とは時代が異なるものの、このパンデミックから学べることは少なくない。実際、速水の著書を読むと、マスク不足や物流の遅延、船内での蔓延などコロナ禍に通じるエピソードが多いことに驚かされる。ただ、現時点で最も注目すべき点は「後流行」の存在だろう。
これまでのところ、新型コロナ流行の波はスペイン風邪の「前流行」とかなり似ている。そうだとすると、新型コロナも2021年春には下火になる可能性がある。ただ、それが流行の終息を意味するとは限らない。油断すると「後流行」に火が付くかもしれないのだ。
特に、流行から1年が経つことで懸念されるのがウイルスの変異だ。スペイン風邪のように強毒化しないにせよ、ようやく接種が始まったワクチンが効かなくなる可能性がないとは言えない。どうすれば感染防止と社会・経済活動を両立させられるかという難題は、春以降も引き続き考えていかなければならないということだ。
速水の著書には、「人類とウイルスの第一次世界戦争」という副題がついている。スペイン風邪の流行が第1次大戦と重なったからだが、同時にウイルスとの戦いにも「第二次世界大戦」があるのだ、と示唆しているのだろう。実際、出版後の2009年には「豚インフルエンザ」のパンデミックが発生し、速水も同書を加筆している。ただ、今振り返って豚インフルエンザが「世界大戦」の名に値すると考える人は少ないだろう。
では、現在直面している新型コロナがそれに当たるのだろうか。実は、それさえ「先触れ」に過ぎないのかもしれない。そもそも速水が同書を著した際に想定していたのは、致死率も感染力も新型コロナを凌駕する強毒性鳥インフルエンザなのだ。そのウイルスは今も日本を含む世界で養鶏場を次々に襲い、「ヒト・ヒト感染」の力を獲得する機会をうかがっている。ウイルスとの戦いは「アフターコロナ」でも続くのだ。
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!
松林 薫